はじめに
フレッシュコンクリートは、建設工事において不可欠な材料であり、構造物の強度や耐久性を決定する上で極めて重要な役割を果たします。打設されたコンクリートが所期の性能を発揮するためには、適切な作業性が確保されていることが不可欠です。作業性とは、コンクリートの混合、運搬、打込み、締固め、仕上げといった一連の作業を、材料分離を生じることなく容易に行える程度を示す性質です。この作業性を評価する最も一般的かつ基本的な試験方法の一つが、スランプ試験です。本稿では、日本国内で広く用いられているコンクリートのスランプ試験について、その定義、目的、具体的な手順、一般的な目標値、影響要因、意義と限界点、そして関連する日本工業規格(JIS)について詳細に解説します。
スランプ試験の定義と目的
定義
スランプ試験は、まだ凝固していないフレッシュコンクリートの流動性を評価するために行われる試験です 。試験の結果として得られる「スランプ値」は、スランプコーンと呼ばれる特定の形状の容器に詰められたコンクリートが、その容器を取り除いた後に自重によって沈下した垂直方向の距離を示すものです 。この沈下の大きさ、すなわちスランプ値は、センチメートル(cm)単位で表されます 。複数の情報源でほぼ同様の定義が示されている ことから、スランプ試験は日本の建設業界において確立され、広く理解されている概念であることがわかります。これらの定義は一貫して、垂直方向の沈下量を流動性の指標と捉えている点に共通性が見られます。
目的
スランプ試験の主な目的は、フレッシュコンクリートの作業性を評価することです 。作業性には、コンクリートが適切に混合され、運搬され、打設箇所に配置され、締固められ、そして所定の表面に仕上げられるまでの容易さが含まれます。スランプ値は、コンクリートの硬さから流動性までを示す指標となり、値が大きいほどコンクリートは柔らかく、流動性が高いと判断されます 。この試験を通じて、使用するコンクリートが特定の用途や施工方法に適した流動性を有しているかを確認することができます 。スランプ試験は、コンクリートの基本的な性質であるコンシステンシーを測定することで、施工の容易さを間接的に評価する役割を果たしていると言えます。コンシステンシーは、コンクリートの流動性や変形に対する抵抗性を示す指標であり 、スランプ値はこのコンシステンシーを簡便に把握するためのものです。
スランプ試験の準備と手順
試験器具
JIS A 1101 に規定されているスランプ試験に必要な主な器具は以下の通りです 。
- スランプコーン: 上口径が 100 mm、下口径が 200 mm、高さが 300 mm の金属製で、厚さが 1.5 mm 以上であることが求められます。また、試験時にコーンを安定させるための押さえと、持ち運び用の取っ手が適切な位置に取り付けられています 。この規格で定められた正確な寸法は、試験結果の標準化と、異なる場所や時期に行われた試験結果の比較可能性を保証するために重要です。
- 突き棒: 直径が 16 mm、長さが 500 mm から 600 mm の鋼製または金属製の丸棒で、先端は半球状に加工されています 。
- 平板: 十分な剛性を持ち、水を通さない平らな板で、通常は鋼製です。大きさは一般的に 0.8 m × 0.8 m 以上、厚さは 3.0 mm 以上とされています 。
- 検尺: スランプを測定するための定規や巻尺で、最小目盛りが 1 mm または 0.5 cm である必要があります 。
- その他: コンクリートをコーンに詰めるためのスコップ、コンクリートを混ぜるための練り板、平板が水平であることを確認するための水準器などが準備されます 。
供試体の作成
試験に使用するコンクリートの試料は、試験対象となるコンクリートのバッチを代表するものでなければなりません。採取は、コンクリートの練混ぜ後、速やかに行う必要があります 。コンクリートは時間経過とともに凝固が始まるため、試験は迅速に行い、水和反応や環境要因によるスランプ値の変化を最小限に抑えることが重要です 。
測定方法
JIS A 1101 に準拠したスランプ試験の具体的な手順は以下の通りです 。
- 器具の設置: 水準器を用いて平板が水平な場所に設置されていることを確認します 。スランプコーンの内面と平板の上面を湿った布などで拭き、清掃します 。スランプコーンを平板の中央に置き、足でしっかりと固定します 。
- コーンへの充填: コンクリート試料を、ほぼ等しい容積の3層に分けてスランプコーンに充填します(各層の高さは約 1/3 程度) 。
- 締固め(突き): 各層を突き棒で25回均一に突き固めます 。突き方は、外側から渦巻き状に中心に向かって行い、コーンの側壁近くではコーンの傾斜に平行に、中央付近では垂直に突きます 。この突き固めの操作は、各層を均質にし、空隙を減らすために重要です。ただし、突き固めによって材料分離が生じる恐れがある場合は、分離しない程度に突き数を減らす必要があります 。
- 上面の均し: 最上層を突き固めた後、コテや突き棒の長軸などを用いて、コンクリートの表面をスランプコーンの上端に合わせて平らに均します 。突き固めによってコンクリートの上面がコーンの上端より低くなった場合は、少量の同じコンクリートを足して均します 。平板上にこぼれたコンクリートは取り除きます 。
- コーンの引き上げ: スランプコーンの取っ手を両手でしっかりと押さえ、足を平板から離します。その後、直ちにスランプコーンを静かに鉛直方向に、2~3秒かけて(高さ 30 cm)連続して引き上げます 。コーンは、ねじったり横方向に動かしたりすることなく、真上に引き抜く必要があります 。
- スランプの測定: コンクリートが沈静した後、スランプコーンの上面(引き上げ前の高さと同じ)から、沈下したコンクリートの頂部中央までの垂直距離を測定します 。測定は、0.5 cm単位で行います 。
- 記録: 測定したスランプ値をセンチメートル(cm)単位で、0.5 cm刻みで記録します 。試験の日時、場所、バッチ番号など、関連する情報も記録します 。
- 再試験: コンクリートがコーンの中心軸に対して著しく偏って崩れたり、せん断状に崩壊したりした場合は、その試験結果は無効とし、新しい試料を用いて再試験を行います 。コーンにコンクリートを詰め始めてから引き上げを終了するまでの時間は、3分以内に行う必要があります 。この時間制限は、コンクリートの凝固が試験結果に影響を与えるのを防ぐためのものです。異常な形状のスランプは、コンクリートの凝集性や安定性に問題がある可能性を示唆しています。
一般的なコンクリートの種類ごとの目標スランプ値
コンクリートの種類や用途によって、目標とされるスランプ値の範囲は異なります。以下に、一般的なコンクリートの種類ごとの目標スランプ値の目安を示します。
- 構造用コンクリート:
- 一般的な建築物の構造部材に使用されるコンクリートでは、スランプ値は通常 15~18 cm 程度が適切とされています 。
- 土木構造物においては、かつてはスランプ 5~12.5 cm の平均値である 8 cm が一般的な目標値とされていました 。
- しかし近年では、鉄筋量の増加や施工性の向上を目的として、土木分野でも 12 cm 程度のスランプ値を標準とする傾向があります 。一部のガイドラインでは、一般的な鉄筋コンクリート構造物の設計スランプ値を 12 cm とすることを推奨しています 。
- 場所打ち床版に用いられるコンクリートでは、単位水量を少なくするためにスランプ 8 cm が標準とされることが多いですが、現場内での運搬条件などにより流動性が必要な場合は、高性能 AE 減水剤などを用いて 12~18 cm に調整されることもあります 。
- 酷暑期におけるコンクリート打設では、目標スランプを 21 cm とし、高性能 AE 減水剤(遅延形)を原則として使用する場合があります 。これは、高温下でのスランプ低下を抑制し、作業時間を確保するための措置です。
表 1: 構造用コンクリートの一般的な目標スランプ範囲
| 用途 | 一般的なスランプ範囲 (cm) | 関連スニペット |
|---|---|---|
| 一般的な建築構造物 | 15~18 | |
| 一般的な土木構造物(従来) | 5~12.5(平均 8) | |
| 一般的な土木構造物(近年推奨) | 12 | |
| 場所打ち床版 | 8(標準)、12~18(必要時) | |
| 酷暑期コンクリート | 21 |
近年、土木分野で標準スランプが 8 cm から 12 cm へと見直される背景には、職人不足による省力化の推進や、耐震性向上のための鉄筋量増加などがあり、従来の 8 cm スランプでは作業効率が悪くなっているという側面があります 。スランプ 12 cm であれば、荷下ろし時点での許容範囲が広がり、作業性が大幅に改善されることが期待されます 。
- 舗装用コンクリート:
- 舗装用コンクリートは、高い強度と耐久性が要求されるため、構造用コンクリートと比較して低いスランプ値が用いられます。
- JIS A 5308 では、舗装用コンクリートのスランプ値として 2.5 cm と 6.5 cm が規定されています 。
- 機械施工による舗装では、スランプ 2.5 cm の硬練りコンクリートが用いられることが多く、この場合、大型の施工機械が必要となります 。
- 人力による舗装では、作業性を考慮してスランプ 6.5 cm のコンクリートが用いられることがあります 。
- スリップフォーム工法による舗装では、スランプ 4 cm、空気量 5.5% を標準とすることが一般的です 。
- 一部の施工業者では、コンクリート床版の強度向上やひび割れ抑制のために、スランプ値 15 cm 以下、場合によっては手作業での施工が困難なほど低いスランプ値を提案することもあります 。舗装コンクリートに低いスランプ値が求められるのは、交通荷重や環境の影響に耐えうる緻密で強度の高いコンクリートを確保するためです。施工方法によって最適なスランプ値が異なるのは、締固めや表面仕上げの効率性を考慮するためです。
- 高流動コンクリート:
- 高流動コンクリートは、流動性が高く、狭い箇所や鉄筋が密集した箇所への打込みに適したコンクリートです 。
- 高流動コンクリートの流動性は、通常のスランプ試験ではなく、スランプフロー試験によって評価されます。スランプフロー試験では、コンクリートの広がり直径を測定します 。
- 目標スランプフロー値は、用途や指針によって異なり、45 cm から 70 cm 以上となる場合があります 。日本建築学会の指針では、高流動コンクリートの目標スランプフローを 55、60、65 cm としています 。免震基礎やコンクリート充填鋼管(CFT)など、締固めが困難な部位への適用を想定した研究では、目標スランプフローを 50 cm や 70 cm とする場合もあります 。高流動コンクリートでは、通常のコンクリートよりも流動性が著しく高いため、スランプ試験では適切な評価が難しく、水平方向への広がりを測定するスランプフロー試験が用いられます。
スランプ値に影響を与える要因
コンクリートのスランプ値は、配合、骨材の種類、混和材の種類、温度など、様々な要因によって影響を受けます。
- 配合:
- 水量: 水量が多いほどコンクリートは柔らかくなり、スランプ値は大きくなります。逆に、水量が少ないとスランプ値は小さくなります 。単位水量(コンクリート1立方メートル当たりの水の量)が 1.2% 増減すると、スランプは約 1 cm 増減するとされています 。ただし、過剰な水の使用はコンクリートの強度低下やひび割れのリスクを高めるため注意が必要です 。水はコンクリート中の粒子間の摩擦を減らし、流動性を高める主要な要因ですが、適切な強度と耐久性を得るためには、水セメント比を適切に管理することが重要です。
- セメント量: 一般的に、セメント量が多いと、同じ水量でもコンクリートの表面積が増加するため、わずかにスランプが低下する傾向があります 。
- 骨材の配合: 細骨材と粗骨材の割合(細骨材率)はスランプに影響を与えます。細骨材率が高い場合、細粒子の表面積が増えるため、同じスランプを得るためにはより多くの水が必要となることがあります 。また、粗骨材の単位容積質量が大きいほどスランプは大きくなる傾向があります 。骨材の粒度分布も重要で、粒径の異なる骨材が適切に混合されているほど、空隙が少なくなり、所要水量が減少するため、スランプにも影響が出ます。
- 水セメント比: 水セメント比はコンクリートの強度に直接影響する重要な指標ですが、スランプ値とも関連があります。水セメント比が同じであれば、単位水量が多くても少なくても強度はほぼ同じになりますが、スランプは単位水量に依存します 。目標スランプを達成するためには、水セメント比とのバランスを考慮し、必要に応じて混和材を使用することが重要です 。
- 骨材の種類:
- 骨材の最大粒径、形状、表面の粗さ、粒度などもスランプに影響を与えます 。角張った骨材や表面が粗い骨材は、丸みを帯びた骨材に比べて表面積が大きいため、同じスランプを得るためにはより多くの水が必要となります 。骨材の種類を変更した場合、所要水量や細骨材率などの配合を調整する必要が生じることがあります 。骨材の吸水率もスランプに影響を与える可能性があり、吸水率の高い骨材を使用する場合は、配合時に表面水を考慮する必要があります。
- 混和材の種類:
- AE 減水剤や高性能 AE 減水剤などの混和材は、単位水量を減らしても同程度のスランプを維持したり、同じ水量でより大きなスランプを得たりする効果があります 。空気連行剤(AE剤)は、コンクリート中の空気量を増加させ、わずかにスランプを増加させる可能性があります 。混和材の種類や添加量によってスランプへの影響は異なるため、配合設計においては混和材の特性を十分に理解する必要があります 。
- 温度:
- 気温やコンクリートの温度が高いと、セメントの水和反応が促進され、時間の経過とともにスランプが低下しやすくなります 。特に暑い時期には、運搬中にスランプが大きく低下することがあります 。練混ぜ時に冷却水を使用したり、ミキサー車に遮熱対策を施したりすることで、温度上昇を抑制し、スランプ低下を遅らせることができます 。コンクリート温度が 30℃、スランプ値が 18 cm 程度の生コンクリートを 1~1.5 時間運搬すると、スランプ値が 6 cm 程度低下する場合もあると報告されています 。
スランプ試験の意義と限界点
意義
スランプ試験は、フレッシュコンクリートの流動性を現場で簡便かつ迅速に評価できる非常に重要な試験方法です 。試験結果は、コンクリートが所定の作業性を満たしているかどうかを即座に判断する材料となり、打込みや締固めといった作業のしやすさの目安となります 。また、異なるバッチのコンクリートの品質を比較し、配合や材料に問題がないかを確認するための品質管理ツールとしても活用されます 。スランプ値は、コンクリートの打込みやすさ、締固めやすさ、そして表面の仕上げやすさと相関関係があるため 、適切なスランプ値のコンクリートを使用することで、構造物の品質確保に貢献します 。
限界点
一方で、スランプ試験はコンクリートの作業性に関する全てを評価できるわけではありません 。スランプ試験は主にコンシステンシー(流動性)を測定するものであり、材料分離抵抗性、ポンプ圧送性、仕上げ性といった他の重要な作業性に関する性質は直接評価できません 。同じスランプ値を示すコンクリートであっても、使用する材料や配合によってこれらの性質が異なる場合があります 。また、スランプ試験は、非常に硬いコンクリート(低スランプ)や非常に柔らかいコンクリート(高スランプで崩壊しやすいもの)に対しては、適切な評価が難しい場合があります 。高流動コンクリートのような非常に柔らかいコンクリートの評価には、スランプフロー試験の方が適しています 。さらに、試験結果は試験者の熟練度や操作方法によって影響を受ける可能性があり 、コンクリートの長期的な性能や耐久性に関する情報は得られません 。骨材の品質やその変動も、スランプ試験だけでは十分に把握することができません 。したがって、スランプ試験の結果は、他の試験結果や現場の状況と合わせて総合的に判断する必要があります。
日本におけるスランプ試験に関する規格
日本におけるコンクリートのスランプ試験方法は、JIS A 1101:2020 「コンクリートのスランプ試験方法」 によって規定されています。以前の規格は JIS A 1101:2005 でした 。
JIS A 1101 では、スランプ試験に使用する器具(スランプコーン、突き棒、平板、検尺)の寸法や材質に関する要求事項が詳細に定められています 。また、試料の準備、コーンへの充填方法(3層に分けて充填)、各層の突き固め回数(25回)、コーンの引き上げ速度(300 mm の高さに対して 2~3 秒)、スランプの測定方法などが具体的な手順として規定されています 。スランプ値の測定単位はセンチメートル(cm)であり、0.5 cm 単位で記録することが求められています 。試験結果が異常な場合(不均一な沈下や崩壊)の再試験の条件や、試験結果の報告事項(試験日、バッチ番号、最大骨材寸法、スランプ値など)も規定されています 。粗骨材の最大寸法が 40 mm を超えるコンクリートの場合、試験に用いる試料からは 40 mm を超える骨材を取り除くことが明記されています 。建設現場におけるスランプ試験の頻度については、JIS Q 1011:2024 に規定があります 。これらの規格に準拠することで、日本国内のどの現場においても、標準化された方法でスランプ試験が実施され、信頼性の高い結果が得られることが保証されます。規格の定期的な見直しは、試験方法の精度向上や、実際の施工状況への適合性を高めるために行われています。
まとめ
スランプ試験は、フレッシュコンクリートの作業性を評価するための基本的かつ重要な試験方法です。本稿では、その定義から手順、目標値、影響要因、意義と限界点、そして関連する日本の規格について詳細に解説しました。スランプ試験は、コンクリートの品質管理において不可欠なツールであり、適切な施工と構造物の性能確保に貢献しています。しかし、スランプ試験だけではコンクリートの全ての性質を評価できるわけではないため、他の試験や現場の状況と合わせて総合的に判断することが重要です。
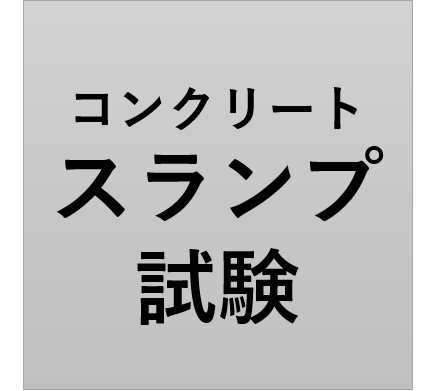

コメント